
龍谷大学 You, Unlimited
Need Help?
Faculty of Economics
経済学部現代経済学科

客観的なデータ分析能力と計画立案に基づいて、具体的な問題解決策を提示できる人材へ
Projects プロジェクト紹介
産業経済プログラム
▼解決を目指す「社会課題」
老舗企業の持続可能性
老舗企業と不易流行 経済学の視点から
京都老舗の本質に迫り未来へのアイデアを紡ぐ


近井 優斗さん
現代経済学科 2年生(大阪府立北千里高等学校 出身)
フィールドワークで探究する老舗企業の持続可能性
地域産業活性化プロジェクトで「老舗企業の持続可能性」という課題と向き合いました。そのなかで創業100年以上の企業を調査して一冊の書籍にまとめ、発表する取り組みを行いました。
取材を重ねるなかで気づいたのは、情報を吟味して分析する重要性でした。例えば、後継者不足に着目した場合、単に少子高齢化の問題ととらえるのではなく、時代の変化に適応しながら伝統を守り続ける難しさという視点も必要です。課題の本質に迫るには、現地調査が不可欠でした。フィールドワークを通じた最も大きな学びは、理論と実践の融合です。取材先では「今日まで継続できているのは、取引先と従業員のおかげ」と口を揃えて語っていました。このことばの背景には、単なる商取引を超えた老舗ならではのファミリーシップを軸とした経営戦略が見えてきます。伝統をどのように継承し、発展させるべきか。地域文化継承の当事者意識が芽生え、その責任の重さを感じています。
SEE MORE

辻田 素子教授
現代経済学科
[専門分野]中小企業論、地域産業論
伝統と革新が織りなす京の老舗に現代のビジネスモデルを考える
産業経済プログラムの「地域産業活性化プロジェクト」では、京都の老舗企業を対象として「不易流行」の本質に迫ります。老舗は、地域社会との深い関わりをもちながら伝統の継承と革新を両立してきたビジネスモデルです。
その経営理念や事業承継の知恵を、徹底したフィールドワークを通じて探究していきます。具体的にはまず、経営者から企業の理念や哲学を学びます。そして、現場での就業体験や社員・取引先へのインタビューを重ねます。さらに地域の祭礼や景観保全活動など、老舗を支える地域社会との関係性にも目を向けて多面的な調査を展開し、これらの成果を一冊の書籍にまとめます。学生たちは一連の過程を通じて、老舗経営の真髄に触れ、フィールドノートの作成や調査の作法を体得し、考察を深めていきます。「伝統と革新」という普遍的なテーマに正面から向き合うことで、現代社会における持続可能な経営のあり方を考える力を養います。
SEE MORE
応用政策プログラム
▼解決を目指す「社会課題」
地球環境の危機
経済学の視点から環境問題の解決策を探り
持続可能な社会の実現をめざす


藤本 昌瑛さん
現代経済学科 3年生(京都府 京都共栄学園高等学校 出身)
経済学の視点から環境問題を分析し持続可能な地球環境の実現をめざす
環境経済学では、経済学的な視点から環境問題を学びます。地球温暖化のメカニズムを理解し、その対策として政府が行う課税や規制が社会にどのような影響を及ぼすのかを経済学の諸原理から考察します。
特に印象深いのは、排出量取引の簡易実験を通じて環境政策への理解を深められたことです。企業の利潤最大化や消費者行動など多角的な視点から、政策のメリット・デメリットを学び、実践的な知識が身につき、環境は現代を生きる私たちだけでなく将来世代の資産でもあると認識できるようになりました。授業を受けたことで自分の生活を見直すようになり、節電やゴミの削減といった問題に対する向き合い方も変わりました。環境問題にはさまざまな要因があり、長期的な視点が重要です。これからの社会を担う世代のために、住みやすい地球にするために、まずは身近な問題から行動を起こしていきたいと考えています。
SEE MORE

李 態妍教授
現代経済学科
[専門分野]環境経済学、環境政策論
環境経済学の学びを通じて社会課題の本質的な解決力を養う
応用政策プログラムの「環境経済学」では、環境問題を経済学的な視点から徹底的に分析します。日常的な生活から生じるごみ問題、都市公害、温暖化といった複雑かつ多様な地球環境問題に対して、単に現象を理解するだけでなく、より根本的な解決策を提案できる力を身につけていきます。
経済実験を通じて、個々人が環境問題の原因者であり、同時に解決の主体者ともなることを、学生たちに実践的に理解してもらいます。さらに、外部性や政策手段、エネルギー源の選択、環境保全と経済開発のバランスなど、多角的な視点から環境問題にアプローチし、政府、企業、個人それぞれの役割と責任を明らかにしていきます。理論だけでなく、実際の行動変容をうながす授業を実践することで、環境配慮に関する当事者意識を高め、持続可能な社会の実現に向けて具体的な行動を起こせるよう支援しています。
SEE MORE
経済データサイエンスプログラム
▼解決を目指す「社会課題」
デジタル社会における専門人材の育成
加速化するデジタル社会に対応できるスキルを養い
データサイエンスの力で社会課題を解決に導く
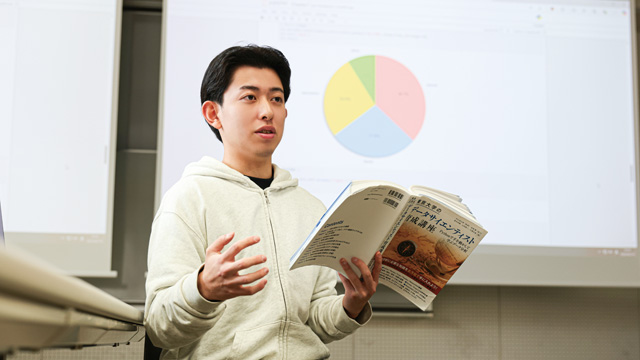

矢島 和樹さん
現代経済学科 2年生(N高等学校 出身)
データサイエンスで広がる知見社会課題解決への実践的アプローチ
経済データサイエンスプログラムをとおして、日々蓄積される大量のデータを分析し、社会課題の解決に応用する手法を学んでいます。プログラミング言語「Python」を用いて、データの整理から分析、可視化まで実践的なスキルを磨いています。
この授業の特徴は、単にデータ処理を行うだけでなく、その結果をどのように解釈し、社会に還元できるかを考えることです。授業で学んだ内容を自宅でも繰り返して取り組むことで、知識や技術の定着がすすみ、日常の小さな疑問から時事問題まで、データに基づいた根拠のある意見を述べられるようになりました。他の授業のレポート作成にもこの技術を活用するようになり、より説得力のある考察ができるようになったと実感しています。今後ますます加速するデジタル社会にも適応できるようデータ分析スキルをさらに磨き、多様な社会課題の解決に貢献していきたいと考えています。
SEE MORE

松木 隆教授
現代経済学科
[専門分野]計量経済学
データサイエンスの力を駆使して多様な社会課題の解決をめざす
デジタル技術の発展により、あらゆる場面でデータの活用が求められています。経済データサイエンスプログラムは、現代に必要不可欠なデータを適切に処理し、活用する能力を育成する実践的なプログラムです。
「Python」によるプログラミング技術を中心に、データの収集・整理から可視化、統計分析まで、データ処理の基礎を体系的に学びます。Pythonを学ぶことは、データ活用やAI技術の理解にもつながります。また、NumPy、SciPy、Pandas、Matplotlib、Scikit-learnなど、実務でも広く使われているライブラリを活用しながら、実社会に即したスキルも養っていきます。データを効果的に処理し、可視化・分析できるようになれば、社会課題を客観的にとらえ論理的に解決できる力が身につき、AI時代の社会変化にも柔軟に対応できる人材になりうるはずです。学生には、このプログラムで得た能力を活かし、幅広い分野での活躍を期待しています。
SEE MORE
Seminars ゼミ紹介
現代経済学科 新居 理有ゼミ

経済・財政問題
データ分析と理論を通じて課題を明らかにし
実践的な政策を提言できる力を養う
松田 理莉緒さん
現代経済学科 3年生(愛媛県 済美高等学校 出身)
新居ゼミでは、マクロ経済学や財政政策を基盤に、現代社会が抱える経済的・財政的な課題をデータ分析や理論を通じて明らかにし、実践的な政策を提言します。ゼミ活動の一環として参加した公共選択学会の学生の集いでは「政治とカネの問題を考える」をテーマに論文を発表しました。政治資金収支報告書という膨大なデータから必要な情報を抽出・分析する過程で、統計的な分析力とともに、社会課題を多角的に考察する力が身につきました。獲得したスキルをもとに、卒業論文では「新幹線が与える経済効果」を探究したいと考えています。
[主な卒業論文テーマ(現代経済学科)]
- 人口減少時代における日本の雇用システムの再構築
- ふるさと納税の現状と地方経済の活性化に向けて
- 日中両国における起業意識の比較分析〜GEMデータ〜
- 能登地方における地震活動と石川県の不動産価格の関係
- 新NISAが日本経済に与える影響
- インバウンド消費の増加に影響を与える要因分析